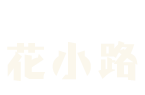木枯らしがぴゅうぴゅうと、街の通りを吹き抜けていく、寒い昼下がりのことです。
ふみやくんはひとりで、るす番をしていました。お母さんはまだ帰ってきません。
話し相手のいないふみやくんは、つまらなくて、寂しくて、しかたがありませんでした。
ひたいを窓にべったりくっつけて、空のようすをながめていましたが、急に天国のパパの声が、聞きたくなったのです。
けれどもふみやくんは、いまだにパパの死を理解できないばかりか、天国がどんなところかも、よくわかっていませんでした。
また、生きていたころのふみやくんのパパは、あまり家にいることはありませんでした。仕事のつごうで遠い町に住んでいたからです。
でも、そのぶん電話を入れ、ふみやくんのまわりで起きたどんなにささいなことにでも、いつもきちんと耳をかたむけてくれたのです。
だからふみやくんは、電話をすればいつだってパパのやさしい声が聞けると思っていたからです。
けれども電話番号を知りません。でもそれは、ふみやくんにとって、たいした問題ではありませんでした。
ふみやくんはさっそく、プッシュホーンのボタンを手当りしだいに押していきました。
ルルルル……、ルルルル……。
「はい、森ですが」
女の人が出ました。
「もし、もし、パパいますか……?」
「えっ、パパ……、どこのパパなの?」
「ぼくのパパ……」
「パパのお名前は?」
「うーんとねえ……、はやし……」
「あらまあ、よく似てるけど少しちがうわね。ママにもう一度番号を確かめてもらいな
さいね。それじゃねえ、バイバイ」
電話は、ガシャッと切れました。
ふみやくんはあきらめません。受話器をぎゅっとにぎったまま、また別の番号を押してみました。
ルルルル……、ルルルル……、ルルルル……、ルルルル……。
今度はなかなか出ません。ようやく、呼び出し音がとまったかと思ったら、
「だ、だれだ!」
すると、いきなりこわい男のひと声。ふみやくんは思わず、受話器を少し耳からはなしました。
電話をとった男は、ある家にしのび込んだあきすねらいでした。びくびくどきどきしながら家にしのび込んだところへ、突然の電話。
あきすはすっかりどぎもを抜かれてしまい、あわてて受話器を取ってしまったのです。
ふみやくんは、そんなことは知りません。
「もし、もし……、パパですか……?」
あきすはそのあどけない声に、またもやぎくりとし、電話を切ることなどすっかり忘れて、受話器を耳にあてつづけました。
「ねえ、パパなんでしょう……?」
あきすは用心しながら、あきすに入る前に見た表札の名前をいいました。
「丹野だが、きみは誰だね……?」
「ふみや……」
「いったい、どこへ電話してるんだい?」
あきすのひたいにはびっしりと、玉のような汗をかいています。
「天ごくのパパ……。パパじゃないの……?」
(天国のパパ……?)
あきすはどうやら、まちがい電話であることに気づきました。ほっと胸をなでおろすと、今度はとてもしゃくにさわってきました。
(よりによって、こんな時に電話がかかってくるなんて、いったいぜんたいどうなってるんだ! それも、子どものまちがい電話ときてるじゃないか!)
あきすは心のなかでそう叫ぶと、いらいらしながらいいはなちました。
「ぜんぜんちがうな!」
けれどもふみくんは、あきすねらいのどこかに、パパのおもかげを感じていたのです。
「そお……? でも……、パパのような気がする」
あきすはまた、言葉につまりました。つとめていた会社がとつぜんつぶれ、長いこと仕事にもありつけないありさまでした。そこで悪いこととは知りながら、生まれてはじめてあきすに入ったのです。
「ねえ、パパ。いつかえってくるの?」
するとあきすの口から、思いがけない言葉がぽろりとこぼれました。
「天国は遠いところだから、そう簡単には帰れないんだよ。そのうちにパパのほうから電話しよう。なん番だったかな?」
「パパ、でんわ番号をわすれちゃったの? よくおぼえていてよ」
ふみやくんは家の電話番号を伝えていると、
「ピンポーン」
受話器のおくから、インターホンの呼びりんが聞こえてきました。どうやらお母さんが帰ってきたようです。
「きっとかけてよ。じゃあねえ!」
と、電話が切れました。
あきすねらいは受話器をおくと、はっとわれに返りました。
男はさいわいにもまだ、なにも盗んでいません。
(ああ、もしもあの子から電話がかかってこなかったら、ぼくは泥棒になるところだった。明日から気持ちを入れかえて、もう一度がんばってみよう!)
男はしのび込んだ裏口から、そっと出ていきました。
それから二、三日過ぎたある日のことです。
ルルルル……、ルルルル……。
ふみやくんの家の電話が鳴りました。ふみやくんは急いで受話器を取りました。きのうもおとといも、待ちかねていた電話です。
「わかるかい?」
「うん、パパでしょう!」
ふみやくんの顔がぱっと、かがやきました。
「元気にしてたかい?」
「うん! パパは?」
「元気だとも」
男は、駅前の公衆電話からかけています。
「ママね、おしごとはじめたんだよ」
「どんな仕事かな?」
「おさけのむとこ」
「そうか、近いのかい?」
「うん、うちの近くだよ。え〜とね、花小路」
「ほお、花小路か。昔ながらのいい街だ」
男はつとめていたころ、よく通っていたなじみの街です。
「パパは?」
男は返事につまりました。いまだに仕事につけない自分が情けなくなり、それでつい、こんなうそをついてしまったのです。
「そうか、ぼくもこっちで新しい仕事について、はりきっているところなんだぞ」
「どんなおしごとなの?」
ふみやくんは少しもうたがっていません。
「花屋さんさ。天国で一番人気のある仕事なんだよ」
「じゃあ、いそがしくて、またかえってこれないんだね……?」
ふみやくんの声が、しゅんとしました。
男はあわてていいました。
「そ、そのかわりまた電話するから、ふみやくんこそ元気にしているんだぞ」
「うん、パパもね! またでんわしてね」
電話を切ると、男は仕事を求めて駅前から十日町、小姓町、寺町と、あてもなく歩き回りました。きょうは朝から雪が降り続いていて、身を切るような冷たい一日です。
気づくと花小路の守り神・三島神社を通り抜けるころには、日はとっくに暮れてしまい、遠くに見える花小路の店みせの看板に灯りがともりはじめていました。
男は、久しぶりに花小路に立ち寄ってみたくなりました。数年ぶりの花小路です。
路地には昔のままの古くて小さい店が立ち並び、店の格子戸から漂ってくるおいしい料理の匂いや、どこからともなく聞こえてくるカラオケの音色に、
(少しも変わってないな)
男は、当時をなつかしむように歩いていくと、いつしか花小路の正面入り口にそそり立つ、アーチのところまで来ていました。
そのアーチもなかった遠い昔、花小路の入り口のこのあたりを、『花小路の思案のしどころ』と、呼ばれていました。
なぜそう呼ばれていたかというと、大人たちは決まってこの場所に立ち止まると、そのさきから聞こえてくる三味の音色や、陽気な笑い声に心がはずみ、さらに見えてくる色とりどりの灯りに、気持ちはどんどん引き寄せられていきました。すると大人たちは腕を組み、さて立ち寄ろうか、それともこのまま立ち去ろうか、ああ〜『ここが思案の
しどころ』と、あれこれと思い悩んだからです。
時は流れ、時代のようそうが少しづつ変わりはじめると、花小路のにぎわいも次第に消えていきましたが、それでもなおこの街には、ほかのどの街にもない、ふしぎな魅力にあふれているのです。
朝から降り続いていた雪もいつしかやみ、男はかじかんだ指に息を吹きかけながら、元映画館のあった角を曲がると、あたりは急に薄暗くなり、もう一つの守り神・幸稲荷大明神の前に、小さな花屋さんが見えて来ました。
それはどこにもあるような小さな花屋さんでしたが、窓からこぼれる明かりが、男にはとてもまぶしく感じられたのです。
店のおくでは、小柄で人のよさそうなおばあさんが、花たばをつくっていました。
(おやっ……?)
入り口のガラス戸に張り紙があって、『店員さん募集』と、書いてあります。
男はすぐに気持ちが高ぶりましたが、それもすぐにしぼんでいきました。
それは、今までいくつかの会社をたずね回りましたが、長引く不況でなかなか雇ってもらえず、いつも断られてばかりいたからです。
けれども次の瞬間、男はとびらのノブを握っていました。
「あ、あのう……、まだ募集しているんでしょうか……?」
と、男はおずおずとたずねると、おばあさんは花たばをつくる手をとめて、ふり向きました。
「ええ、まだ募集していますよ」
「わたしのようなものでも働かせてもらえるでしょうか? 花の名前もよく知らないのですが……」
すると、おばあさんはにっこりほほえみながら、椅子をすすめました。
「花の名前なんか、やる気さえあればじきにおぼえられますよ。ところで運転免許証をお持ちですか? 市場へ行くにも、配達するにも、運転できませんとね」
「はい、免許証はこの通り持っています。運転は得意で事故は一度も起こしたことはありません」
男は免許証を取り出して見せました。
花屋さんは、おじいさんとおばあさんとでやっていましたが、おじいさんがこのあいだ、市民会館へ花たばを届けに行った際、階段から落ちて足の骨を折る大けが。
ところが、おじいさんのけがは思った以上に重く、退院がいつになるかわかりません。
そこで二人は思い切って、店員さんを募集することにしました。
「お給料のほうなんですけど、あまり上げられませんけど、それでもよろしいですか?」
「はい!」
話しはとんとん拍子にはこんでいき、
「では、明日から来てくださいな」
男は店を出ると、つぶやきました。
「うそからでたまこととは、よくいったもんだ」
ふみやくんに思わず口走ったことが、ほんとうになってしまったのです。
翌日から男は、おばあさんと一緒に花の市場へ行ったり、仕入れた花をお店に並べたりしながら、一生懸命働きました。
そうしてなん日か過ぎると、男は自然と花の特長や、名前をおぼえられるようになりました。するとふしぎなことに、花の名前をひとつおぼえるごとに、気持ちまでまたひとつ、やさしくなっていくような気がしてなりませんでした。仕事がなくてうちひしがれていたあのころが、まるでうそのようです。
「ほんとうによく働いてくれて、大助かりよ。おじいさんもいい人が来てくれたって、とても喜んでますよ」
おばあさんは、はじめの約束よりも少しお給料をはずむことにしました。
いつしか春になりました。いまでは男は仕入れもまかせられるようになり、市場へもひとりで出かけるようになっていました。お客さんからの評判も上々です。
そんなある日のことです。若いおかあさんと四才くらいのかわいい男の子が、花屋さんにやってきました。花屋さんのおばあさんとは、顔なじみのようです。
おばあさんが話しかけました。
「大変でしたね。あれから、かれこれ一年、もう落ち着きましたか?」
「おかげさまで、なんとか元の生活に戻れそうです。でもこの子がまだ、天国のパパから電話がかかってくるといってきかないんです」
「無理もありませんよ、突然のことでしたからねえ」
男の子を見つめるおばあさんのまなざしは、やさしさであふれていました。
「はい。これからお墓参りにいって、よく話をしてきかせようと思っています。おそなえのお花、お願いできますか?」
(えっ! 天国のパパ……、電話……)
店のすみで花をより分けていた男は、どきりとしました。あの日のできごとがまるで、きのうのように思い出されます。
「おまたせしましたね」
お墓にそなえる花ができました。
「ふみやくん、いきますよ」
男の子はふしぎそうに男を見つめていましたが、おかあさんに手を引かれるままに、店の外へ出ていきました。
あれから男は、時おりふみやくんに電話を入れていましたが、そのたびに心が痛みました。このままパパのふりをつづけることが、はたしてふみやくんにとっていいことなのか、とても悩んでいたところだったのです。
男は、ふみやくんの元気な姿を見ると、ようやく決心がつきました。
それからそっとお店を出ると、ふたりのうしろ姿に深々とおじぎをしました。
(あの時はありがとう、ふみやくん)
花小路のすみ切った青い空のどこかで、アゲヒバリがうれしそうに鳴いていました。